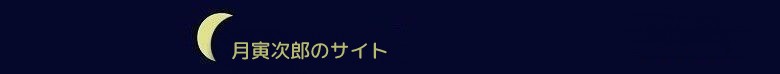
満願寺温泉 川湯
最終更新日: 作者:月寅次郎

満願寺温泉(川湯)は、近隣の黒川温泉とは対象的に、鄙びた感じのいいとこです。
観光地化しておらず、商業的な雰囲気が無いため、落ち着いて静かに過ごせます。
温泉の隣に洗い場があるというのが、また実に良く、昭和の日本の風景を今に残しています(川上にあり、しかも2段になっているのがポイント)
8月の暑い時期に入浴してみましたが、湯温はそれほど高くはなく、ゆっくり浸かっていられる温度です。
湯上がり後も汗がドバドバ出続けるといった感じはありません。夏に浸かるにはいい感じです。一方で、冬季は涼しく感じる可能性も。
単純泉で臭気もほとんど感じられないため、泉質としては個性の薄い温泉ではありますが、泉質云々よりも、川面のせせらぎや集落の生活感をしみじみ味わいながら、風情を楽しむ温泉です。
浴槽のへりに停まるトンボ、ハヤ(オイカワ)が川中を泳ぐのを眺めながら、開放感溢れるお湯に浸れます。
よく晴れた日に入浴すると、川面にきらめく陽光が、庇の裏側に反射して、ゆらゆらとうごめく様子も美しいものです。
(天気の良い日に入浴の際は、庇(天井)を見上げてみるのをお忘れなく)
満願寺温泉の住所、地図
住所:熊本県阿蘇郡南小国町満願寺2299
満願寺温泉 川湯:目次
「日本一恥ずかしい温泉」とは?

『日本一恥ずかしい温泉』というのは、満願寺温泉(川湯)のキャッチコピーです。
上の画像は、まさに入浴中のものですが、このように、川向うの道を時折車が通り抜けていきます。
実に恥ずかしいですね。
とはいえ、ガードレールの高さが丁度良い位置にあるため、部分的に目隠しになってくれます。
(こちらからは運転席の人が見えませんし、向こうからも見えにくいです)
ただこれは、あくまでも車高の低いセダンタイプの車の場合であって、アイポイントの高いミニバン車や、トール系ワゴン車の場合は、この限りではありません。
(歩行者、自転車も同様です)
しかしながら、普通の人であれば、「裸の人がいる!」と判った時点で「そちらの方向を直視するのは、いかがなものか?」という心理作用が働くものです。
(男性の場合は)気にすることなく、堂々と湯に浸かっていましょう。
万一目が合ってしまった場合は、ニコッと笑って会釈する心の余裕もお忘れなく。
(向こうの方も恥ずかしく感じるものです。堂々としている方が、相手も気を使わずにすみます)
満願寺温泉 『川湯』に入ってみる

脱衣場は、川の上に差し掛かる庇の裏手にあります。
対岸の車道から見る限りでは、(上の画像のように)上手に隠れるようになっています。

こちらがその脱衣場、極めて開放的です。
前述のように、対岸からは見えませんが、横方向からは丸見えです。
足元には板が置かれています。
靴を脱いだ後は、この板の上で脱衣します。
入浴料は200円。箱に投入するタイプです。
お釣りが出るわけではありません。事前に100円玉を2枚用意しておくとスムーズです。
衣類や荷物は、湯船の上にせり出ている棚に置いておきましょう。

『湯銭箱』と書かれています。
階段を数段降りると、そこは開放的な川沿い温泉です。

手早くかけ湯を済ませ、素早く湯船に浸かりましょう。
湯船に入るまでは、それなりに抵抗感がありますが、湯に入ってさえしまえば、それほど恥ずかしいものでもありません(男性の場合)
社会通念上、裸でいても不自然な場所ではありませんので、通報されることはありませんが、公然わいせつ罪に抵触しないものか、ふとそういう考えが頭をよぎってしまう、そんな不思議な場所です。

温泉の湯面は、川面の高さとあまり違いません。
そのため、あたかも川に浸かっているような気分がしてきます。
かけ流しのお湯は、そのままダバダバと川に流れ出ていきます。
この、だばだばと水の流れていくさまが、また良いのです。

湯に浸かりながら、上流方向を眺めたところです。
8月に入浴してみましたが、湯温はそれほど高くはなく、ゆっくり浸かっていられる温度です。
上がった後も汗が出続けるといった感じはありません。夏に浸かるにはいい感じです。
(一方で、冬季は涼しく感じる可能性も)
単純泉で臭気もほぼ無いため、泉質云々よりも、川面のせせらぎや山村の生活感をしみじみ味わいながら、風情を楽しむ温泉です。
浴槽のへりに停まるトンボ、川底をつついて回るハヤ(オイカワ)、そういった自然の風景に浸れます。
(時折向かいの道を自動車が通り、その度に現実に引き戻されますが、それもまた一興です)

湯船は2つあります。上の画像は、下流側の湯船です。
緑色の柄付きタワシが下がっている部分は、湯船の上にぐっとせり出ていますが、これが前述の脱衣類を置くための棚として機能しています(棚の裏側です)
この川湯の棚は(庇も含めて)、なかなか上手にできていて、棚や庇としての役割を果たしながら、目隠しとしても機能しています。
最も素晴らしいのは、「過剰に覆いすぎていない」という点です。
人目を気にして覆いや壁を作りすぎると閉鎖的となってしまい、この素晴らしい開放感が失われてしまいます。
それでは『角を矯めて牛を殺す』というものです。
この川湯の開放感は、必要最小限の「目隠し」とのバランスによって成り立っており、実に絶妙です。
このように作ったのは、恐らくかなり昔の時代の方なのでしょうが、実に粋なセンスだと感じ入ります。
(今の時代では、なかなかこのような思い切った設計は難しいものです)

上手方向にある、洗い場です。
『野菜、食器、洗い場、入浴、足つけ禁止』とあります。
上水道が普及する以前、井戸水が使われていた時代では、このような川の洗い場は生活の一部となっていました。
今の時代では、見かけることも少なくなりましたが、往年を知っている世代にとっては、懐かしい限りです。

雲間から陽光が差し込んできました。
太陽がさんさんと降り注ぐと、川面もキラキラと輝きだし、湯船の底石も美しく浮かび上がります。
(天気の良い日を選んで入浴するのがおすすめです)

太陽が輝きだすと、湯面に陽光が反射し、庇の裏に光がゆらめきだします。
ゆらゆらと揺らめく光の波を見ていると、外から丸見えの場所でスッポンポンでいるのも忘れそうになります。
(いや、そこまではないか…)
上の画像では、単にまだらに写っているだけで、この状態をうまく撮影できませんでしたが、天気の良い日に訪れた際は、是非とも庇の裏を見上げてみてください(実にきれいです)

この、満願寺温泉(川湯)の良いところは、自然の川ベリという好環境であるにも関わらず、入浴者が少ないところです。
筆者は、人の混み合う温泉があまり好きではありません。
できることであれば、誰も居ない湯船を独占し、ゆったり気のままに過ごしたいものです。
「外から見えるから恥ずかしい」という羞恥心が、この川湯に浸かる者を少なくしています。
是非とも、いついつまでもこのままの、外から丸見えの温泉であって欲しいものです。
満願寺温泉 周辺を散策

(クリックで拡大)
地元の方々に迷惑をかけないよう、そ~っとやってきて、静かに入浴したいところです。
(自然とそういう気持ちになる、安らかな温泉です)
こういうところが、今の時代の日本に残っているということは、実にありがたいことです。

川の上に差し掛かる庇の下が『川湯』です。
左側に見える階段は、満願寺温泉(共同浴場)の入り口で、こちらは恥ずかしくない普通の温泉です。

手前の橋の上より上流方向を撮影したところ。
画像中央の、歩行者専用橋の奥に小さく見える庇が、満願寺温泉の『川湯』です。

満願寺温泉共同浴場の裏手に行ってみましょう。
ひっそりとして、奥には祠が建っています。

苔むした手積みの石垣が、時代を感じさせます。
上に通じる小道は、どれも細く、人が歩くだけの幅しかありません。
そこがまた、侘び寂びと、風情を感じさせてくれます。

小学校跡の碑です。
現在は公民館となっており、この集落に学校はありません。

こちらは、通学用のバス停です。
(たまたま、ホンダのスーパーカブが停まっていますが、実にこの風景にマッチしています)
『道幅狭し』の標識がある通り、周辺道路は幅が狭く、離合の難しい箇所があります。
対向車と鉢合わせとなることもありますので、スピードは落とし気味で走行しましょう。
満願寺川の流れ

満願寺川の流れです。

川べりには草が生い茂っており、川自体が自然を濃く感じさせます。
カワニナも生息しているでしょうから、ホタルもいることと思います。
蛍の舞う季節に、もう一度訪れてみたいものです。

護岸は昭和の時代になされたと思われるもので、往年の雰囲気を残しています。
画像左側の、自販機のある家屋が、村内唯一の商店です。
趣があって、これがまたいい感じです。
趣を感じさせる建物

立護山満願寺にある、趣のある楼門

印象的な窓枠の、二階建て納屋
ガラスのいくつかに破損が見られるのが残念ですが、このような凝った窓枠を修理してくれる業者さんも、今の時代にはそうそういないのでしょう。

軒先が印象的な古い納屋?

満願寺温泉館の入口正面には、古い家屋が残っていますが、壁面の補修に古いトタン看板が流用されています。
これがまた、実に興味深いです。

錆や塗料の劣化で読み取れない部分もありますが…、
「日本徴兵保険申込書◯種 第七特務◯ 阿蘇郡分団長橋本」
…と書かれてあります(◯は判読不明)
日本徴兵保険について
日本徴兵保険は、1911~1912年に使用されたとの記録が残っています。
1941年(昭和16年)に広告掲載があったという説も
1911~1912年というと、日露戦争後、一次大戦前です。
1904年日露戦争、1905年ポーツマス条約調印、1906年韓国統監府開庁・伊藤博文初代統監、1909年伊藤博文射殺事件、1910年南満州鉄道会社設立、1911年辛亥革命に対して出兵、1912年清王朝滅亡・溥儀退位、第一次世界大戦1914年…と、なかなかにきな臭い時代ではありました。
徴兵保険は入営した場合は保険金の支払いを受けられ、入営しなかった場合には、支払った保険料が払い戻されるというものだったそうです。
「徴兵を受けて国を離れた場合でも、後に残された家族の経済的心配をすることなく、立派にお国のために役目を果たすことができる」と説明されていたもようであり、徴兵という人生の一大事に備えた保険商品であったようです。
● 関連ページ:渋沢栄一記念財団、日本徴兵保険のページ
● 関連ページ:保険毎日新聞「みちくさ保険物語」(PDF)
● 関連ページ:保険会社の広告(徴兵保険の広告)

看板のすぐ脇には、昭和の時代のトイレ煙突がそのまま残っています。
こういった古い時代の遺物がそのまま残っているのが、満願寺温泉の趣のあるところです。
時が止まったかのような感覚を覚える温泉地であり、誇張した表現が許されるならば『千と千尋の神隠し』のように、異世界に入り込んだ感すらあります。
総じて静かで慎ましく、往年の時代の人の息吹と、里山の自然の両方が感じられる、素晴らしい温泉です。