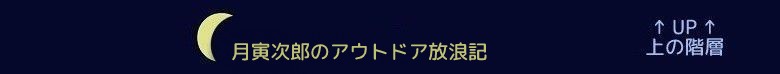
ブライトホルン登山後記4(必要な体力レベル)
最終更新日: 作者:月寅次郎
ブライトホルンに登るための基礎体力
それではブライトホルンに登るには、実際どの程度の体力が必要なのでしょうか?ここでは、最低限必要な体力ではなく、安全に登って降りてこられ、なおかつ余裕を持って眺望を楽しめるだけの体力として考えてみましょう
● 目次のページに戻る >> ブライトホルン(4164m、雪と氷の白い世界)
「テント泊・連泊縦走装備の背負重量で、コースタイムからあまり遅れない程度に歩ける」というのが、一つの基準になるかと思います(私見です)
(ザックの重量は、体重のある人なら20kg程度を想定しています。体重の軽い女性もおられますので、一概に何キロと言うのが難しいですが、体重に0.3を掛けたくらいの重さを想定しています)
日帰り登山の場合は、ザック重量は5kg~8kg程度で収まりますし、その場合はコースタイム通りに歩ける人がほとんどです。ですが、テン泊装備の状態で同じスピードを保つのは、とたんに難しくなります
重量物を背負うとその分体力を使い、酸素の消費も激しくなり、脳と筋肉が「もっと酸素が欲しい!」と言い続ける状態で登ることになります
ブライトホルンでは、それだけの重量を背負うことはありませんが、逆に酸素が薄いため、上記と同じように、「もっと酸素が欲しい!」の状態となり、結果的に近似した状態になります
少し条件的に厳しいのではないかとも思いましたが、酸素の濃い場所である程度の重量を背負って動けるようでないと、酸素の薄い場所でははなはだ心もとないです
高山病の症状が出て、頭がガンガンする状態で登るのはおすすめできませんし、前述のように「余裕を持って眺望を楽しむ」こともできません
またある程度の重量のザックを背負って活動できるようであれば、脚力と体幹、身体のさばき方などもしっかりしてきますので、足元が不安定なさまざまなシチュエーションにも、上手く対応できるのではないかと思います
累積標高差、水平距離、コースタイムなどの指標を活用しよう!
自分の背負っているザックが、普段どの程度の重量なのか、計ったことの無い方もおられると思いますし、コースタイムなど全く気にせずに歩いている方も多数おられると思います登山の楽しみ方も様々ですので、それらを否定するものではありませんが、3000m以上の山に登られる方は、そのコースの水平距離、累積標高差、コースタイム、ザックの重量と自分の疲労具合などを、常に意識するようにして下さい(記録を取って数字として残しておくと良いです)
登山経験を重ねていくと、そのコースの累積標高差、水平距離、設定コースタイムを見るだけで、体力的にどの程度のコースなのか、おおよその予想がつくようになります
ブライトホルンの累積標高差は、400mあるかないかというわずかなものですが、標高4000mを超えるところから400m登らないといけないというのが、難しいところです
しっかりとした基礎体力と心肺機能があれば、それほど問題のあるコースではありませんが、累積標高差やコースタイムを全く気にかけたことがない人がブライトホルンに登ろうというのは、あまりおすすめできません(止めたほうが良いと思います)
例えば、「累積標高差1200m、水平距離12km程度のコースなら、テン泊装備でも問題なく行動できます」というように、(それまでの山行経験を元に)自分の体力を数字を使って自分なりに語ることができるというのは、それも登山の技量の一つの重要な要素です
前のページで、「自分の体力レベルと高所耐性を、自分の言葉で語れない方は、3500m以上の山に登るべきではありません」と、かなりキツイ物言いをしてしまいましたが、 「彼を知り、己を知れば、百戦殆うからず」です
まず、自分自身がどれだけ背負えて歩けるのか、それすら把握せずに高山に挑むのは「百戦危うい状態で登っている」と言っても、過言ではないでしょう
スイスの山岳救助ヘリコプター

画像はスイスの山岳救難ヘリコプターが、着陸して登山者を収容しているところです

スイスでは山岳救助は有償です。日本のように救助費用を税金負担というのはありません
オートルートを歩いている際には、何度も救助用ヘリコプターを飛ぶのを目にしました
山中まで飛んできて救出していく場合もあれば、下山後のキャンプ地に着陸してきたこともあります
遊覧飛行でヘリコプターに乗る分には良いのですが、救難目的では、なるだけお世話になりたくないものです
さて、(非常に簡単ではありますが)高山病と必要な体力レベルについて解説してみました。
次のページでは、ブライトホルンでのザイルの扱いについて取り上げてみます
ブライトホルンでは、数多くのツアー登山客が「コンティニュアス・ビレイ」でガイドと電車繋ぎになっていますが、あれには果たしてどれだけの意味があるのでしょうか?
「全員を繋いでいたら、一人が足を滑らせたら、逆に全員落ちちゃうんじゃないの?」というありがちな疑問について、私見を綴ってみました
● 次のページ >> ブライトホルン登山後記5(ザイルを繋ぐ意味)