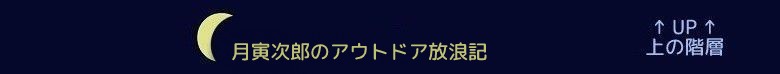
シュイロン氷河 - Glacier de Cheilon/Swiss

スイス・オートルートの旅、7日目に訪れた「シェイロン氷河」です。
オートルートではさまざまな氷河が堪能できますが、ここまで近くに寄れる氷河は珍しいです。
ここまでの工程も結構長く、体力を要しますので、山好きの人かガイド付きの登山ツアーしか来ません。観光客がほとんど来なくて、山と湖、氷河が堪能できるいいとこです。
シュイロン氷河(Glacier de Cheilon)、撮影日2013年8月6日 Swiss
※ 発音は、「シロン」にかなり近い感じの「シュイロン」(だと思います)
● 関連ページ:世界屈指のトレイル「オートルート」を歩く(全工程とコース概要)
シュイロン氷河(遠景)

遠方から望遠で撮影したシュイロン氷河。
遠くから見ているため実感が湧きませんが、それなりに大きな氷河のようです。
S字型にうねりながら落ちている様子は、もう少し近くに寄ると見えてきます。
この時間帯は、まだきれいに晴れており、陽の光に照らされた雪面がきらきらと輝いて、非常に美しかったです。
(この後徐々に曇ってくるので、最後の方は写真の写りが悪くて少々残念)
この後、えっちらおっちら歩いて、氷河に近づいていきました。

氷河全体が見渡せる位置まで近づきました(小一時間くらいかかったかな?)
「やったー!」と、喜ぶ筆者。

シュイロン氷河とDix小屋
いいですね。素晴らしいロケーションの山小屋です。

中央右下に4人の登山パーティが見えます。
人影があるおかげで、氷河の広大さが際立ちます。
本当に、デカくて大きくて巨大です(語彙!)
訪れる人も少ないため、静謐な感じがあり、しばし無言になります。
(このあたりはモワリー氷河とは対照的で、山好きな人におすすめの氷河です)

氷河が切れ落ちている箇所
近くで見ると質量感がスゴイです。
シュイロン氷河を歩く

氷河の上には、岩や小石がゴロゴロしている箇所もあります(そうでない場所も)
この岩は、氷河に削られて押し流され、氷河の上に乗った状態でゆっくりと移動しています。
氷の状態が安定していたので、横断して上を歩きました。
下流の方は氷が安定しているため、歩ける可能性は高いですが、実際に歩けるかどうかは、その時その時の各自の判断です。
時期と状態と装備と経験にもよりますので、一概には言えません。
(今は氷河の縮退が激しいので、割れ目も多くなってるかもしれません)
氷河の周辺はルートが不明瞭ですので、道がなくても地図読みで行ける人推奨です(もしくはガイド付きで)

所々に、クラック(氷の割れ目)も見られました。
割れ目は、浅くて細く、クレバスというほどではありません。
割れ目の部分が薄青く見えるのは、氷河らしさを感じるところです。

融水が、小川となって氷河の上を流れているところ。
よく見ると、川の色がほの蒼く、これもまた氷河ならではです。

氷河の上で記念写真。
この頃から雲行きが怪しくなってきて、周囲が暗くなってきました。
「もっと写真撮りたいけど、天気が悪化する前に峠を超えねば」…とか考えてるところです。

シュイロン氷河の末端付近まで歩いてきました。
よくよく見ると、左側奥の山あいにDix湖が在るのが判ります。
雪渓ではなく「氷河の上を歩いた」というのは、なかなか良い思い出です。
(以前「針ノ木大雪渓」を降りたことがありますが、あれはあれでとても楽しかったですけどね)

峠に登っている途中から、氷河を見下ろしたところです。
もう小さくて見えなくなりましたが、右に位置する岩山の(左側)頂上にDix小屋があります。
岩山の奥をぐるっと回って氷河の上を渡り、ここまで登ってきたわけです。
さようなら、シュイロン氷河。
また逢う日まで。
シュイロン氷河の位置・地図
GoogleMapでの位置です。
見て分かる通り、人里離れた場所にあります。
シュイロン氷河の周囲
Cabane des Dix(Dix小屋)

シュイロン氷河の目の前にある「Cabane des Dix(Dix小屋)」
(Cabane = 小屋、フランス語、発音はケバン)
ここに泊まって氷河を眺めながら過ごしたかったのですが、この後天気が崩れる予報が出ていたため、パスして下山しました。
悪天候で山小屋に閉じ込められてしまい、数日間下山できない恐れもあったためです。
Col de Riedmattenと、Pas de Chevres(峠)

シュイロン氷河からアロラ村に降りるには、急峻な峠を超えなければなりません。
峠は2箇所。
Col de Riedmatten(リードマッテンのコル(鞍部))と、
Pas de Chevres(ヤギ峠)という、長いハシゴの掛かった峠です。
(どちらを通ってもOK)
遠方から見ると、これら2つの峠は、ほぼ垂直にしか見えません。
右よりの最低鞍部が「Pas de Chevres」、左端のやや高い位置にある鞍部が「Col de Riedmatten」です。

技術的な難易度が高いわけではありませんが、浮き石も多く、岩がゴロゴロしていますので、初心者が先行している場合は、大きく距離を開けましょう。
上の画像のように、一つのハシゴに一度に二人乗って、距離を詰めて登るのは、あまりおすすめできません。
荷重的にも余裕が少なくなりますし、もう一人の動き方次第では(ハシゴの固定が甘いと)思わぬ揺れ方をする場合もあります。
(このハシゴは、わりとしっかり固定されてるように見えましたし、メンテナンスもされているはずですが、雪と氷に晒される場所では、土台となる岩自体も風化しますので、常に安全とは限りません)
周囲の登山者の技量を一目で判断するのも、山の技量の一つです。
「この人、山に慣れてない…。」と感じたら、距離を置いて近づかないのが一番です。
直下に位置取りしている場合は特にです。本人に悪気はなくても、石を落とされたりして事故に巻き込まれるケースがあります。
「落(ラーク!)」という声掛け自体も、知らなかったりします。
「落(ラーク!)」は日本の掛け声ですが、
英語圏での落石時は「ROCK, ROCK, ROCK, ROCK, ROCK!!」と連呼して叫びます。
日本の場合、「ラァーーーーク!」と、長く伸ばす人も多いですが、「ROCK」の場合は短めに連呼です。
「落石が止まるまで、"ロック"と叫び続ける」ということになっています。富士山など外国人登山者の多い山に登る場合は覚えておきましょう。
(「ラーク!」も「Rock」も、語感が似ているのでたいてい通じますけどね)
● 関連ページ:HOW TO AVOID ROCKFALL(英語)

こちらは、Col de Riedmattenを下から見上げたところ。
(筆者が通ったのは、こちらの峠)
岩稜帯ですので踏み跡が付かず、道が分かりにくですが、これがルートです。
急峻ですが歩いて登れます。技術的にテクニカルではありません。
岩にペイントされた赤白のマーキングは、ルート表示です。
マーキングの色が青白ではないので、「危険性の少ない一般ルート」ということになっています。
とは言っても、赤白ルートの中でも、かなり青白に近い難易度だと思います
(もうほんの少しでも危険であれば「青白ルート」になるはず)
スイスの登山コースのマーキング
赤白マーク:山道、ハイキングルート、トレッキングコース等の「ルート」を示している。
ラインの方向は、ルートの方向を示している(分かりにくい場合は、矢印が書き加えられている場合も)
青白マーク:テクニカルなアルパインルートであり、しっかりした山用の安全装備が求められる。
(実際には、荒涼とした岩稜帯で踏み跡が無く、ルートが不明瞭な場合にも青白マークが付いていたりします。これは、平坦地で「落ちる・転ぶ」の危険性は少ないものの、悪天時に視界不良でルートロストとなりやすい危険性を見ているものと思われます)
なお、
青白ルートはアルパインということにはなっていますが、それほど本格的なアルパインを指しているものではありません。
あくまでも、一般的な登山客に向けての注意喚起であり、
「このルートはやや危険なので、経験と知識、体力と装備が伴っている人だけ通るように。鼻歌まじりで歩けるようなハイキングルートではありません」といった感じの意味合いです。
青白よりも危険度の高いルートになると、マーキングが公式に管理されたものでなくなり、単に矢印になったり、マーキング自体が無かったりします。
「自己責任で勝手に登れ。ルートは自分で見つけるか、ガイドに教えてもらえ」…という感じです。
(14日目に登ったベラ・トラ山(3025m)、15日目に登ってシュバルツホルン(3201m)がそうでした)
日本三大キレットはすべて通りましたが、大キレットや不帰の嶮あたりのグレードですと、青白を超えて「ノンマーキング」に相当するかなと思います(槍の穂先もそうです)
ザイテングラートくらいの険しさだと『青白ルート』、ザイテングラートと涸沢ヒュッテの間のなだらかなルートは、『赤白』に相当すると思います。
平たく言うと、道幅が広く、ダブルストックを使ってスタスタ歩けるのであれば、『赤白ルート』
道幅が細く、ここで転倒もしくは滑落すると、骨折・捻挫・そこそこの出血レベルの怪我(要は自力で帰れない)場合が『青白』
滑落イコール即死亡、もしくは大怪我の場合は、「ノンマーキング」という感じです。
(私見ですが、おおむねこのような印象を受けました)
なお、これらの「赤白・青白」マーキングは、スイスハイキングトレイル協会(Swiss Hiking Trail Association)が維持管理しており、毎年調査・点検がなされています(黄色の道標看板も同組織が管理、なんとこれらはスイス憲法にもその規定がある)
● 参考ページ:スイスでハイキングをするときに知っておきたいこと(swissinfo・日本語)
菱形黄色、赤白、青白等の簡略的な説明有り(次に挙げるスイス観光局の方が、説明としてはより具体的で判りやすい)
● 参考ページ:Information on hiking(スイス観光局・英語)
菱形黄色「ハイキングトレイル」、赤白「マウンテン ハイキング トレイル」、青白「アルパイン ハイキング トレイル」が、それぞれ何を意味するのか、詳細な説明があります。
● 参考ページ:Swiss Hiking Trail Association(赤白マークを塗る画像有・ドイツ語)
ディ湖(Lac de Dix)

シュイロン氷河の氷と水は、最終的にディ湖(Lac de Dix)に流れ込みます。
この地域にある湖には、やたらと細長いのものも多いですが、それはたいてい、氷河の侵食谷に水を溜めた「ダム湖」です。
このディ湖は、シュイロン氷河と距離的さほど離れていないこともあり、水中に散乱する岩の微粒子が濃く、水の色もそれに影響されています。
(ドロドロのセメントを、水で薄く溶いたような色をしています)

氷河周辺は氷と岩のガリガリ地帯ですが、少し手前のあたりでは緑も豊かで、美しい高山植物が楽しめます。

ディ湖の南側斜面には、黄色い花が一面に咲き乱れている箇所があります。

近くによると、このような感じの、とても可愛らしい花たちです。

晴れていると、ひじょ~に美しいところです(何もないところが、また良いです)
上の画像中央の岩肌を望遠で撮ると…。

このような感じです(いいですねぇ~)

これは、シュイロン氷河とディ湖の間の中間地点のあたりです(2つの峠は、この右手に位置します)
荒涼とした感じで涸れ沢のようにも見えますが、よく見ると、中央に小さな水の流れがあり、この流れはディ湖まで繋がっています。
涸れ沢の向こうに見える、土手状の堆積物はモレーン(氷堆石)です。
画面左手前にルートが走っているのが判りますが、このあたりは部分的にルートがはっきりしない箇所もあります。
地図読みをしっかりして、自分の居る位置を把握し、進む方向さえ間違えなければ、特に問題はありません。
ただ、常日頃から地図読みをせず、地図を頭にも入れず、道と看板とスマホのGPSに頼って歩いている方は、ガイド付きのツアー等で行くことをおすすめします。
(日本人はほとんど来ないエリアなので、日本人向けツアーなどがあるかどうかは判りませんが)

この日は、同じエリアを歩いていたガイド付きツアー客のうち1名が、疲労で歩けなくなり、ヘリで運ばれていきました。
ちなみにスイスでは、山岳救助ヘリは有料です。
画面左の中央に見えている、小さな赤い物体は、救助用ヘリコプターです。
このあと要救護者を乗せて飛び立っていきました。
● 関連ページ:世界屈指のトレイル「オートルート」を歩く
● おにやんま君(パラコード)の自作
● 月寅次郎のアウトドア放浪記に戻る
● 月寅次郎のDIYページに戻る
キャンプ・登山関連のページ
 おにやんま君(パラコード)の自作
おにやんま君(パラコード)の自作550パラコードを使ったストラップ型の「おにやんま君」の作り方。
使用材料、編み方、留め方など。
 沢靴(ラバーとフェルト)
沢靴(ラバーとフェルト)さまん谷参加メンバーの沢靴一覧と解説です。
花崗岩系の沢にはラバーソールが良くフィットしていました。
 L.W.シットハーネス(モンベル製登山用ハーネス)の装着手順
L.W.シットハーネス(モンベル製登山用ハーネス)の装着手順L.W.シットハーネスの装着手順(備忘録)と、インプレです。
モンベルには、沢専用のサワークライム シットハーネスもありますが、こちらの方が装着感が良かったため、愛用しています。
 実用的なキャンプ用ナイフとは何か?
実用的なキャンプ用ナイフとは何か?オピネル、スイス・アーミーナイフ、超軽量の薄型ナイフ(実測25g)など、ナイフはいろいろ使ってきましたが、大人数でキャンプを楽しむときは、実用的なフィレナイフを携行するようになりました(最も使いやすいので)
元々は釣り用として買ったものですが、何をどうやっても、フォールディングナイフはシースナイフに勝てないのです(携帯性以外は)
堅牢で耐久性に富み、摺動部のメンテナンスなど一切必要ありません
オピネルのブレード開閉が固くなって閉口したことのある方なら、一度検討してみるのも良いでしょう