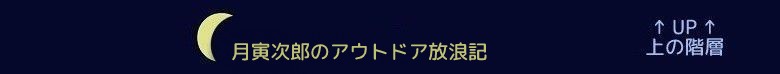
おにやんま君(パラコード)の自作
最終更新日: 作者:月寅次郎

パラコードで作る「虫避けストラップ」です。
釣具店で販売されている「おにやんま君」と同様の効果を狙ったものですが、トンボの外観をそのまま模した「リアルタイプ」よりも幅が広いため、より高い被視認性が期待できます。
(リアルタイプの胴体幅は5~6mm前後ですが、こちらは15~16ミリ程度あり、3倍の太さがあるため、より目立ちます)
● 合わせて読みたい:おにやんま君は効果なし?それとも有り?

装着イメージは、こんな感じ(ザックに付けた場合)
内径21.6mmの大型リングを使っているため、上の画像のように、幅20mmのストラップに取り付けることが可能です。

こちらは、短尺タイプの『パラコードおにやんま君ミニ』
ファスナーに取り付けて、ポケットの引き手(ジッパータブ)として使っています。
こちらは内径18mmのリングを使っています。
材料の調達や自作が面倒な場合は、完成品を購入できます(下のリンク先)
● おにやんま君効果の虫除け(パラコード・ストラップタイプ)(ヤフオク)

ちなみに以前は、下の画像のような「リアルタイプ(自作品)」を使用していました。
『自作 おにやんま君』(初期型・リアルタイプ)

これはこれで悪くはないのですが、風が強いと羽根が煽られることもあり、決して耐久性の高いものではありません。
ピクニックのような山なら良いですが、藪こぎなどしようものなら、すぐに壊れてしまいます。そして何より、いくら精巧に作っても、見た目がダサいです。
「どうしてトンボ付けてるの?」と、訊かれることもあり、その度に説明が面倒です。
ちなみにこの「リアルタイプ」、どのような材料で作っているかというと…、
- 胴体:発泡トレー(黒)
- 羽根:三幸製菓 ミニサラダ のトレイ部分
-
黒色:黒色ビニールテープ(全体に巻き付け)
-
黄縞:3Mスコッチ マスキングテープ(カット&貼り付け)
- 目玉:アルフォート大袋の裏面(アルミラミネート)を貼り付け、マッキー 緑を塗る
- 脚 :ビニールタイ(本体ボディに穴開け挿入)
このリアルタイプをより機能的に改良したのが、下のストラップ型です。
「形状的にトンボに似せることにこだわるよりも、黒・黄の縞模様を強調させ、被視認性を上げた方が効果が高いのでは?」との考えに基づいています。
田畑に張ってある「鳥よけキラキラテープ」や、カラスよけの目玉グッズと同じで、相手を驚かせて警戒させれば良いだけなのですから、リアルに似せる必要性はないのです。
『自作 おにやんま君』(パラコード・ダブルリング)

上の画像は、最初に作ったストラップ型のおにやんま君です。
パラコードを編んで作っているため、風雨に強くタフで、汚れても洗えるというメリットがあります。
リアルタイプよりも幅広で縞々部分も長めのため、被視認性が高く、よく目立ちます。
作りやすいように、両端にキーリングを装着した『ダブルリング型』として制作しましたが、工夫すればリング一つで作れるのではないかと考え、試行錯誤の末完成したのが、現行型の『シングルリング型』になります。
おにやんま君(パラコードタイプ)の作り方
材料、必要な道具(パラコードおにやんま君)
-
4mm径(5/32in)のパラコード(黒/黄 2本)
- キーリング 1個
- ライター
- ニッパー(ハサミでも)
(耐荷重が550ポンド(Lbs)のもの、キロ換算で249kgとなります)
ここで紹介している編み方(フィッシュテール編み)では、70cm x 2本のパラコードで、12~14cmの長さ、幅は15~16mm程度に仕上がります。
ユルユルに編むと16mm幅には仕上がらず、より太くなります。
ビシビシに締め込むと、15mm幅ぐらいまで追い込むことも可能ですが、16mm幅ぐらいまでできればひとまずOKだと思います。
4mm幅・550パラコード を揃えよう
パラコードは、ATWOOD(アトウッド)とROTHCO(ロスコ)が有名です。双方ともアメリカのブランドで、ATWOODはロープ専業メーカー、ROTHCOはミリタリーアイテムのメーカーです。
● パラコード 4mm イエロー (amazonで検索)
● パラコード 4mm イエロー (楽天で検索)
● パラコード 4mm ブラック (amazon)
● パラコード 4mm ブラック (楽天で検索)
キーリング 22mm も必要
筆者が使っているのはニッサチェインのキーリングです。造りがしっかりしており、耐荷重も明記されており、安心して使えます。
● キーリング 22mm (amazon 商品ページ)
● キーリング 22mm (楽天で検索)
2本のパラロープを繋ぐ(溶着)

ライターで炙って、黒と黄のパラコードを溶着させます。
溶かしすぎるとなかなか冷えないため、再びバラけてしまってくっつきにくいこともあります。
溶着が甘いと、途中でバラけたり切れたりします。
何度かやっていると、丁度よい塩梅がつかめてきます。
リングに通す・ベース板に固定

上の画像の要領で、パラコードをリングに通し、ベース板に固定します。
つなぎ目を少しずらしておくことで、完成時につなぎ目が見えなくなり、外観的に良くなります。つなぎ目を屈曲部に持ってくると、強度的にも落ちますので、こちらの方がおすすめです。
リングの反対側は、ケーブルタイとテープを使って固定していますが、しっかり固定できれば何を使っても構いません。
フィッシュテール編み

パラコードを、このような形に組みます。
この通し方は、間違えやすいポイントの一つです。
間違えると、この後の網目が揃いませんので、すぐに判ります。

同じ要領で、どんどん編んでいきます。
(編み方は、フィッシュテール編み)

さらに編みます。
この画像では、やや緩めになっています。
実際には、「紐を締める」と、「紐を上に押しやって隙間を詰める」を、繰り返しながら編んでいきます。
編み上がり

おおよそ編み上がりました。
この時点で、21回編み込んでいます。
ここで一旦ベース板から外し、『締め込み』をかけます。
締め込み

一旦編み上がった状態から、さらに締め込みをかけます。
最初の頃は編み目回数が24回前後でしたが、何度も作っているうちに要領がつかめてきたのか、25~26回程度まで編み込めるようになりました。
(長さが同じであれば、編み込み回数が多いほど、目の詰まった編み方となります)
後述の末端処理もそうですが、この「締め込み」の工程は、慣れ・不慣れの差が出るところです。
(具体的にどうやって編み目を締め込み、ギュッと締まった状態に持っていっているかについては、ここでは明かしませんが、かなり時間をかけて、何度も繰り返し締めることで目を詰めています)
ビシビシに締め込むことができれば、緩みが無くなって目が詰まり、引き締まった外観となります。
締め込みがおろそかですと(最初はさほど目立ちませんが)次第によれてきたり、編み目が寄って隙間が生じたりして、見た目がだらっとした感じになります。

上の画像は、「締め込み」が不十分な例です
(編み目も21回しかありません)
よく見ると、編み目の間に隙間ができているのが分かります。
(ひとつ上の画像と見比べてみてください)
末端処理・抜け止め
※ この工程は、一部ダブルリング型の末端処理画像を掲載しています。作業自体は基本的に同じです。

余ったパラコードを切断し、このぐらいの長さにします。
※ ここでは黒紐のみをカットしています。

ライターの火で炙り、溶けたところを板状のもので押さえ、先端を平たくして抜け止めにします。
周囲をテープで巻いているのは、熱が当たって溶けないための養生処理です。
※ この画像では、黒のみを末端処理しています。
使用したライター『SOTO スライドガストーチ』
● SOTO スライドガストーチ (amazon 商品ページ)
● SOTO スライドガストーチ (楽天で検索)
● 関連ページ:「SOTO スライドガストーチ」の分解修理

上の画像は、シングルリング型の末端処理例です。
やっていることはダブルリング型と基本的に同じです。ただこちらの場合、黒・黄を一本づつ仕上げずに、一度に両方溶かす「一発仕上げ」で、2本のケーブルを互いに溶着させています。
2つのケーブルを溶着させずに、一本づつバラバラに仕上げても、先端を平たく仕上げることで充分な抜け止めとなり得ます。(さほどこだわらないのであれば、一本づつのバラバラでも構いません)
双方を溶着させるかバラバラに仕上げるかは、作業者判断でどちらでも良いと思いますが、いずれにせよ、入念にやろうと頑張りすぎると、編み込み部分まで溶けてしまい、これまでやってきた作業がすべて水の泡となります。(気をつけましょう)
末端処理の失敗事例

熱が当たって溶けた失敗事例がこちら。
リング部分を通るコードが溶けています。
熱を当てる方向を考慮し、熱源の上方向にパラコードがこないよう、位置を考えて熱を加えることがポイントです。
パラコードの末端処理は、最も失敗しやすいポイントです。
編まない状態の末端処理ならさして難しくもありませんが、編んだ後にやるわけですから、「末端部のみを溶かして、編んだ部分は溶かさない」というのが難しいのです。
わたしも何度も失敗しましたが、失敗しても気を落とさずに、また最初からやり直してください。
こういう作業は、失敗を繰り返してそこから学ぶ人ほど、上手に作れるようになります。
締め込みもゆるゆるで末端処理も適当だと、失敗すらしないと思いますが、それではなかなかきれいに造れるようにはならないと思います。
追記
この「ライター焼き」の方法は、一般的に知られているものですが(前述のように)稀に失敗することがあります。
そのため現在は、失敗の起こりにくい別の方法を採用しています。
(具体的な方法は非公開です)
完成品

「パラコードおにやんま君」の完成品です。
全長:約16cm
ストラップ部長さ:約13cm(リング部含まず)
リング:内径21.6mm(耐荷重4kg、破断荷重34.5kg)

裏返した反対側は、このような感じです。

スモールサイズの『パラコードおにやんま君ミニ』
全長:約9~8.5cm
ストラップ部長さ:約6.5cm(リング部含まず)
リング:内径18.5mm(耐荷重2kg、破断荷重18kg)
ストラップ型おにやんま君(自作品)の特徴
いざという時にロープになる
切ってバラすと、70cm程のロープが2本取れます。結んで繋ぐと約140cmとなり、緊急時に役立ちます。
(黄色と黒のパラコードは溶着させて繋いでいます。負傷者の搬送時など、強い荷重をかける場合は、溶着部で切れる可能性が否定できません。溶着部を一旦切断して、本結びやテグス結び等で結び直して使ってください)
高強度で壊れにくく、耐久性が高い
壊れにくく、ぶつけても落としても大丈夫。(折れたり割れたりしません)装着した状態で万一転倒してしまっても、柔軟な素材でできているため身体にダメージを与えにくく、本体も壊れにくいです。
羽根が無いため、風に煽られにくく、悪天候にも強くなっています。
正規品(リアルタイプ)は、細い紐や安全ピンで装着する構造のため、作りとしてはかなり華奢です。
引っかけたりして強い力がかかると、バラバラになったり外れたりする恐れがあります。
登山や渓流釣り、沢登りなどアクティブな要素の強いアウトドアの場合はパラコード型のメリットが強く生きてきます。何でもすぐに壊しがちなお子様の場合も同様です。
汚れても、洗える
アウトドアで使用して泥々に汚れても、洗えます。洗濯機にそのまま突っ込んでも問題ありませんがが、洗濯ネットの使用を推奨します。
編み目に泥や砂が入り込んだ場合や、長く大事使いたい場合や、は、水を張った洗面器等に入れて、柔らかめのブラシで大まかな汚れを落としたあと、衣料用洗剤を使って優しくブラシでこすり洗いをしてください。
(毛足の固いたわし等でゴシゴシやると、毛羽立ちや毛玉が発生することがあります)
被視認性が高い
市販のおにやんま君は、実物を模しているため、胴体の幅が5~6mm程度しかありません。虫から視認されなければ、いくら形状が似ていても全く意味がないのですが、これでは少々心もとないです。
一方のパラコード自作タイプは、幅サイズが約16mmです。
被視認性の高さは「一つの性能」でもありますので、パラコード型の方がかなり目立ちます。こちらの方がハイスペックと言えるでしょう。
(縞模様の面積で比較すると、市販品の3倍以上の性能があります。)
人にはさり気なく、虫にはしっかりアピール
リアルタイプを身に付けていると、「どうしてトンボを付けているの?」と必ず聞かれます。これが度重なると、結構面倒に感じてきます。

上の画像は、ジッパータブ替わりに装着した「パラコードのミニタイプ」ですが、これだとそれほど違和感はありません。
色味は派手で目立ちますが、ザックの盗難予防にもなります。
(同色同メーカーのザックでも、このタブが付いているのは自分のザックだと特定できるためです)
ヤフオクでは「おにやんま君効果の虫除け(パラコード・ストラップタイプ)」の名称で出品しています。
実使用時の感想

沢沿いの登山道でブユ(ブヨ)が出た時の話ですが、虫の目の前で目立つように振ると逃げてゆき、他の人に向かうようになりました。
(その人は結局刺されてしまい、腫れが出て病院に行くことになったので、逆に申し訳なく感じています)
アブやブユなど、複眼で目が大きく、視覚の発達している虫に有効だという印象を持ちました。
(逆に、メマトイのような数ミリ程度の羽虫には、大きな有効性を感じませんでした)
虫側から視認されなければ効果は出ませんので、人の身体の動く箇所・目立つ位置に装着すると効果的です。(前後もしくは左右に、揺れ動くように吊り下げて装着すると、より効果的です)
沢登りでの使用例

実際に装着した時の画像です。
(左から二人目が筆者です。この時は、胸元のサコッシュに装着していました)
沢水に浸かると、わずかながら苔臭くなることもありますし、実際少々汚れもしましたが、洗濯後はビビッドな色合いが復活しました。
なかなかいい感じです。

岩場を登ったり水流の中で立ち込んだりと、アクティブに渓流釣りをされる方なども、わたしのようにパラコード・ストラップ型をチョイスする方が良いでしょう。

このような白く泡立つ急流に立ち込んだ場合でも、問題を感じません。
装着したまま水中に飛び込んだり、急流に逆らって歩いたりもしましたが、構造的に壊れにくく、外れる恐れもありません。沢登りに集中することができました。
なお、ロードバイク乗りの方がヒルクライム練習する際にも適していると思います。
平坦な場所を走る場合、虫に追いつかれることは無いですが、斜度15%を超える急坂だと、ブユを振り切るスピードが出せずに、延々とまとわりつかれる事があります。(多量に発汗している場合は、アブやブユが顕著に寄ってきます)
車両通行量が少なく、木陰に覆われた細い山道はヒルクライム練習にはもってこいですが、虫が多いのが難点です。
● おにやんま君は効果なし?それとも有り?
● 月寅次郎のアウトドア放浪記に戻る
● 月寅次郎のDIYページに戻る
キャンプ・登山関連のページ
 月寅次郎のアウトドア放浪記
月寅次郎のアウトドア放浪記アウドドア関連のトップページです。
 スイス・アルプス「オートルート」を歩く
スイス・アルプス「オートルート」を歩くモンブランから、マッターホルンまで(雨天停滞等もあり、17日かけて歩きました)
・ スタート:シャモニー(フランス)
・ ゴール :ツェルマット(スイス)
・ 距離:約200km
・ 累積獲得標高:約12,000m
・ 峠越え回数:11回
● シュイロン氷河(7日目)
 ブライトホルン(4164m)に登る
ブライトホルン(4164m)に登るブライトホルンはスイスアルプスの山で、標高は4,164m。位置的にはスイスとイタリアの国境付近にあります
西側にはマッターホルン(4478m)、東側にはモンテローザ(4634m)があります
オートルートを歩き終えた後、帰国予定日まで余裕がありましたので登ってみました (全9ページ)
 おにやんま君は効果なし?それとも有り?
おにやんま君は効果なし?それとも有り?市販の「おにやんま君」は効くのか効かないのか、評価にバラツキが出る理由。
有効となる羽虫の種類、効果の出やすい装着の仕方など、まじめに考えてみました。
市販品で「虫が寄ってこない」と表示があるのは誇大表現であり、優良誤認の可能性があります。
 沢靴(ラバーとフェルト)
沢靴(ラバーとフェルト)さまん谷参加メンバーの沢靴一覧と解説です。
花崗岩系の沢にはラバーソールが良くフィットしていました。
 L.W.シットハーネス(モンベル製登山用ハーネス)の装着手順
L.W.シットハーネス(モンベル製登山用ハーネス)の装着手順L.W.シットハーネスの装着手順(備忘録)と、インプレです。
モンベルには、沢専用のサワークライム シットハーネスもありますが、こちらの方が装着感が良かったため、愛用しています。
 実用的なキャンプ用ナイフとは何か?
実用的なキャンプ用ナイフとは何か?オピネル、スイス・アーミーナイフ、超軽量の薄型ナイフ(実測25g)など、ナイフはいろいろ使ってきましたが、大人数でキャンプを楽しむときは、実用的なフィレナイフを携行するようになりました(最も使いやすいので)
元々は釣り用として買ったものですが、何をどうやっても、フォールディングナイフはシースナイフに勝てないのです(携帯性以外は)
堅牢で耐久性に富み、摺動部のメンテナンスなど一切必要ありません
オピネルのブレード開閉が固くなって閉口したことのある方なら、一度検討してみるのも良いでしょう