
刃物研ぎ機 ホームスカッター STD-180E
ホームスカッター STD-180E 使用レビュー
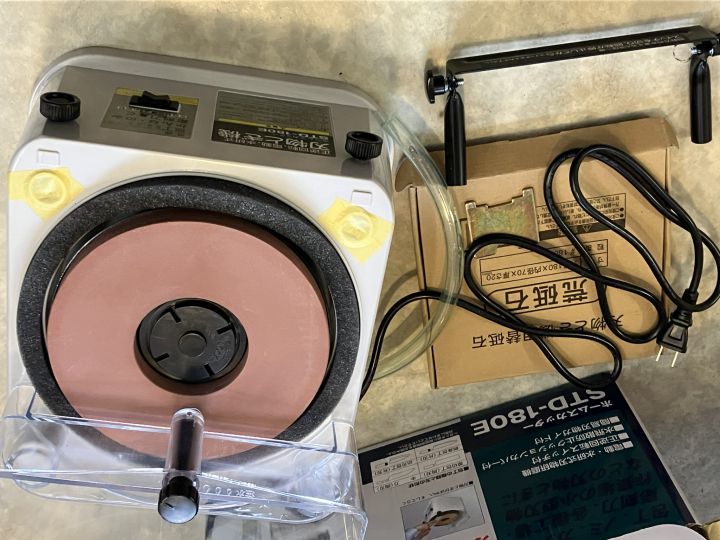
新興製作所 刃物研ぎ機 ホームスカッター STD-180Eの解説ページです(1/4ページ)
2ページ目は、実際の使用例、
3ページは、使いこなし、コツと注意点
4ページは、競合製品との比較 になっています。
(文章量が多くなったため、4ページに分割しました。目次は統一していますので、どのページからでもジャンプ可能です。)
ホームスカッター STD-180E - 目次
ホームスカッター STD-180E 買うならこちら
● 新興製作所 STD-180E (amazon)
● 新興製作所 STD-180E (楽天で検索)
ホームスカッター STD-180E の特徴

こちらが、筆者が購入した「ホームスカッター STD-180E」です。
「刃物ガイド」を取り外した状態です。
ガイド差し込み穴に砥泥が入ると、事後の掃除が面倒なので、黄色のマスキングテームで覆っています。
回転方向を左右に切替可能
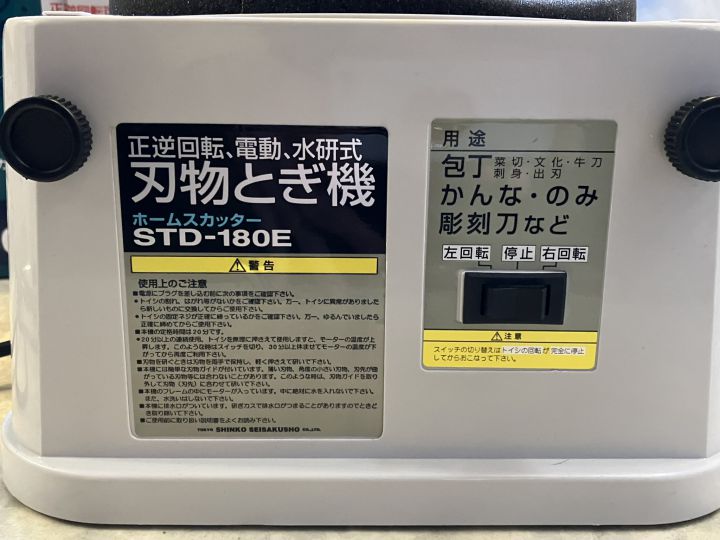
STD-180E、正面パネルとスイッチ。
ホームスカッター
STD-180E
これは新興製作所の研ぎ機の特徴の一つで、最大のメリットです。
(Hikoki GK 21S2(日立)やmakita 9820など、他メーカーの機種にはこの機能がありません)
この手の電動研ぎ機に慣れてしまえば、単一の回転方向でも問題なく研ぐことができますが、それでも順方向に押し付けて研ぐ方が、研ぎやすいものです。
単一方向に回転が固定されていると、片面は順研ぎ、反対面は逆研ぎで研ぐしかありません。
(柄を逆の手に持ち替えたとしても、そうなります)
回転方向が変更できるのは、代えがたいメリットです。
【 注意 】
回転方向を逆にする場合、一旦電源をOFFにして、砥石の回転が停止するのを待ちます。
回転状態でスイッチを反対操作しても、何も変わりません。従来方向のままで回り続けます。
交流電源を利用したシンプルな単相モーターですので、慣性負荷が大きな状態で、瞬間的に正逆回転させると、回転が切り替わらないのです。
回転が切り替わらないだけだと良いのですが、回転速度によっては、モーターに想定外の負荷がかかる場合も考えられます。回転方向を反対にする場合は、砥石が一旦停止してからスイッチを入れましょう。
【 柄はどちらの手で握る? 】
柄は、自分が研ぎやすいと思われる方の手で握って下さい。
前述のように、柄を握る手を変えても、順研ぎと逆研ぎを切り替えることはできません。
円盤型回転砥石ですので、構造上そうなります。
ちなみに手研ぎの場合、柄を左右の手に持ち替えて研げる人は、それほど多くありません。
左右に持ち替えて研ぐ方が、砥石の片減りが抑えられるのですが、これができる人は少ないです。
なお、頻繁に持ち手を変えて研ぐと、柄に砥泥が付着します。
積層強化木やプラ柄の包丁でしたら、気にする必要はありませんが、天然木柄の和包丁の場合は、朴材の木肌に砥泥が付くと、洗ってもなかなか取れません。要注意です。
水飛散防止クッション(スポンジ)

ホームスカッターの特徴の一つが、水跳ね防止のスポンジ「水飛散防止クッション」です。
(上の画像は、スポンジを外したところ)
スポンジは溝に嵌まっているだけですので、摘んで引き上げたり押し込んだりして、高さの微調整が可能です。
スポンジがあるおかげで、砥石から飛び散る水滴の、周囲への飛散が抑えられます。
この『水飛散防止クッション』は、『回転方向の左右切り替え』と並んで、ホームスカッターの2大メリットです。
Hikokiやマキタなど、競合他社にはこの特徴がありません。
無いことは無いのですが、樹脂製であったりするため、包丁の側面を研ぎ抜く時に干渉してしまいます(スポンジだと、柄に当たってもそこだけ柔軟に凹むため、邪魔になりません)
他社でこれと同じ機能を持っている場合、それは新興製作所が供給しているOEM品です。
京セラ(旧リョービ)などがその代表例ですが、製品外観もそっくり同じです。

スポンジの継ぎ目は、このようになっています(接着でつながっています)
なお、刃物を研いでいると、スポンジに刃が当たって切れ目が入ることがありますが、さほど気にすることはありません。
スポンジは別売パーツとして供給がありますので、経年劣化や使用過多でボロボロになった場合、買い直すことも可能です。
● 販売ページ:ホームスカッターSTD-180用部品 水滴防止クッション
透明で見やすい給水容器

給水容器は先代モデルと異なり、透明な樹脂素材に変更されています。
上から覗き込まなくても、水の残量が一目で判るように改善されています。
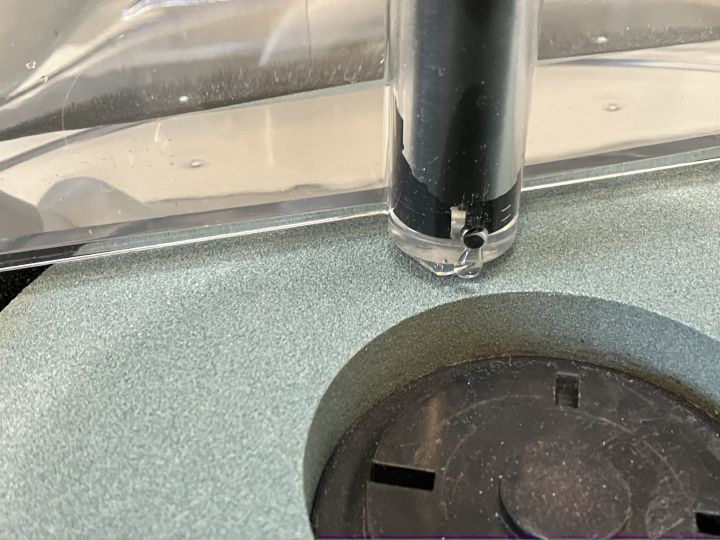
給水容器から水滴が落ちる様子。
黒い棒状のダイヤルを回すことで、水の落ちる量を加減することができます。
(棒に刻まれている溝と、容器の穴がぴったり重なると、「だだ漏れ」になります)
取説によると、「1秒間に1滴落ちるくらいが目安」とされていますが、これはあくまでも目安です。
ちなみに筆者の場合、水量は「やや多め」で使用することが多いです。
砥泥が乗りすぎると、面で当てる場合に刃が暴れやすく、切削効率も落ちるためです。
適正水量は、荒砥、中砥、仕上砥など、使う砥石にもよりますが、電動研ぎ機の場合は「砥泥を活かして柔らかい当たりで研ぐ」よりも「砥粒にしっかり当てる、効率を優先した研ぎ」が重要です(そのための電動パワーなので)
その分、水の飛散も多めになりますが、風呂場で防水エプロンを使って作業することで対処しています。
【 補足 】
滴下水量は、容器内の水量にも左右されます。
水量が少なくなると、充分な水圧がかからず、水の出るスピードが遅くなったり、水滴が出なくなくなったりします。
容器内にある程度の水量がある方が、水圧がしっかりかかり、滴下量も安定するため、水量が1/4以下になった場合は、面倒くさがらずに水を足して下さい。
また、「電動研ぎ機は効率優先」と書きましたが、それは大まかに大体の刃の形状を整える場合の話です。
刃付け時の最後の仕上げや、『カエリ取り』など、繊細な研ぎが必要な場合は、砥石の回転を止め、「手研ぎ」で作業しています。
1.3Aのハイパワー

STD-180Eは、1.3A(アンペア)のハイパワーです。
製品重量は5kgあり、これだけの重量があれば充分です。
(重い分だけ、モーターコイルと磁石が大きいということです)
電動研ぎ機は、刃を押し付けても回転が遅くならないだけの、トルクの強さが重要です。
GK21S2
ですが、カンナなどの面で研ぐ刃物となると、それなりに接触面積が大きくなり、摩擦力も大きくなってきます。
そのため、トルクの大小は重要なポイントです。
包丁の側面を研ぎ抜くような、負荷のかかる作業も試してみましたが、少々強めに押し付けても回転は微動だにしませんでした(これだけのトルクがあれば充分です)
日常的に大型の刃物を整形したり、仕事として刃物研ぎを行う場合は、日立のHikoki GK 21S2 の方が、2.0A+205cm砥石で心強いですが、
STD-180Eの1.3Aと180cm砥石でも、必要にして充分です。
ちなみに、回転数は400/470回転となっていますが、これは電力周波数の違いにより、
東日本は50hzで、400回転
西日本は60hzで、470回転
…で作動するようになっています。
昭和の扇風機と同じで、交流電源をそのまま単相モーターで駆動しているため、電源周波数の違いで回転数も変わります。
簡易刃物ガイド
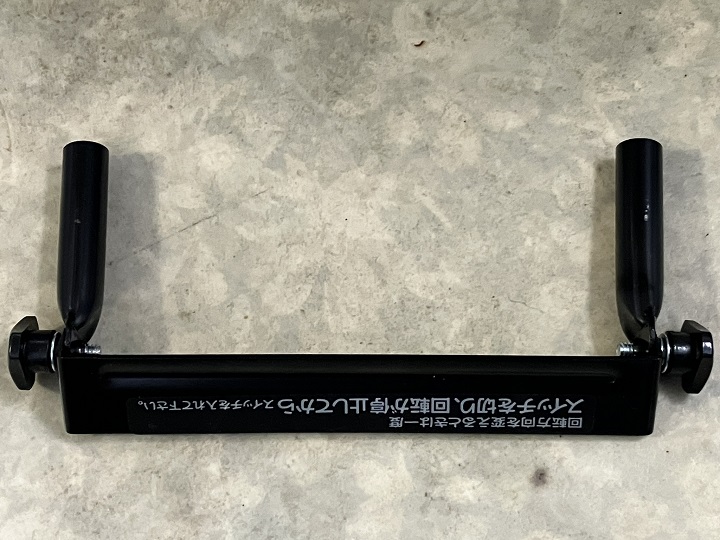
こちらは、刃物の角度を安定させるための簡易ガイドです。
主にノミやカンナ刃などの、片刃でなおかつ、刃筋が直線的な刃物を研ぐ場合に、補助的に使用するものです。
両刃の洋包丁を研ぐ場合は、あまり必要ない、…というよりむしろ邪魔になるかもしれません。
使用しない場合は、抜き取って外しておけばOKです。
なお、STD-180Fに付属の刃物ガイドは、あくまでも簡易的なものです。
しっかりと刃物を固定し、より精密な角度で安定した研ぎを行いたい場合は、「精密刃物支えガイド」付きで、出力も砥石サイズもより大型の上位機種、STD-205Fを使うと良いです。
抜いた後の穴に砥泥などが入ると、作業後の清掃に余計な手間がかかります。
個人的にはマスキングテープを貼って穴を塞ぎ、砥泥が入らないようにしています。
荒砥石と仕上砥石(別売)

荒砥石
#180(純正)
砥粒は、中砥石によく使用される、一般的なアランダム(A)です。
青色の砥石は、#180番の荒砥石です(純正交換用砥石)
こちらの砥粒は、荒砥によく使用されるグリーンカーボランダム(GC)が使用されています。
個人的には未購入で所有していませんが、#6000番の仕上げ砥石もラインナップされています。
#1000番中砥石(赤茶色)は、最初から製品に付属していますが、荒砥石と仕上砥石は、『別売品』の交換用砥石です。
※ 追記(2023年10月)
#6000番の仕上砥石を購入しました。
(純正品ではなくキングの機械研磨用替砥石。この後に解説あり)
ホームスカッター 仕上砥石 #6000

「荒砥石」の本体とパッケージ。
Made in Japanと書かれていますが、砥石は日本製が一番です。
(焼結型の湿式砥石は特にです)

実際に荒砥石を使ってみましたが、切削力は充分で、ゴリゴリと削ってくれます。
上の画像は、荒砥で付いた研ぎ目です。
#180番という粗粒子ですので、研ぎ目も盛大に付きます。

同じく荒砥での研ぎ目です(やや拡大)
この研ぎ目についてですが…、
圧を強めにかけると、相対的に研ぎ目は深くなります。
ただそれだけではなく、研ぐ対象の硬度にも左右されます。
3枚合わせ鋼材の側面を研ぐ場合ですと、硬度が低いですので、研ぎ目が深く入ります。
1枚ものの単層の場合は、側面まで硬度が出ていますので、それほど深くは食い込みません。
また、砥石との接触面積の大小によっても、目の深さは大きく変わってきます。
上の画像の包丁は、単層ステンレス鋼材ですが、硬度と圧力、当たる面積の大小の3要素の組み合わせ次第で、研ぎ目の深さはいかようにも変化します。
(一律にこのような研ぎ目が入るというわけではありません)
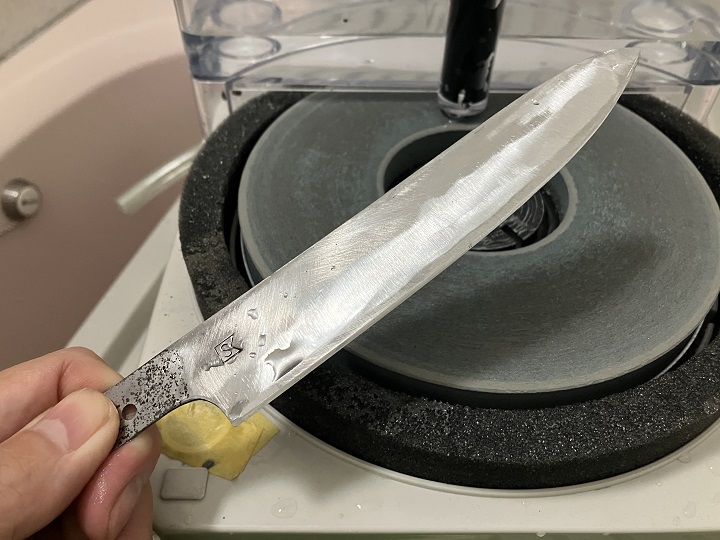
こちらは、荒砥でブレードの側面を研ぎおろしている最中の画像です。
研ぎおろしの途中のため、まだ側面のカーブがあまり取れておらず、多面体のような感じで削れています。
結果的に、当たる面積も狭くなっており、その分研ぎ目も深めに入っています。

こちらは、荒砥での研ぎおろしの最終段階の画像。
一旦スイッチを止め、砥石の回転をフリーにして、手研ぎで仕上げています。
力を入れる度に砥石がくるくる回ってしまいますが、コツを掴むと、それを逆に利用して研げるようになります。
電動器具は切削力が高いため、なだらかなカーブ曲面をつけようと思っても、多面体のようになることもありますが、手研ぎで仕上げると、うまい具合に『角』が取れます。
ここでは、荒砥から中砥石へつなげるために、荒砥の研ぎ目を薄くするイメージで研いでいます。
ブレードに対し直角に入っているのが、電動研ぎによる研ぎ目、斜めに入っているのが、それを薄めるための、手研ぎの研ぎ目です。
うまい具合に、電動で付いた角を落としながら、研ぎ目を薄くすることができました。
(目視による推測ですが、#300~400番程度の研ぎ目に仕上がっていると思います)
同じ荒砥でも、技量次第で研ぎ目をここまで薄く仕上げることが可能です。
一本の砥石で、どれだけワイドレンジに研ぐことができるかというのは、研ぎの技術の一つでもあります。
ホームスカッター 仕上砥石 #6000
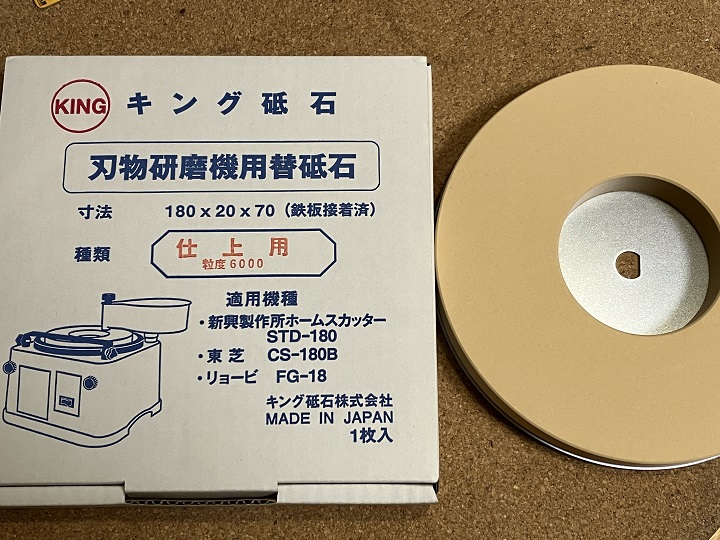
仕上砥石
#6000(純正)
この#6000番の仕上砥石は、純正品ではなく、キングの交換用砥石です。
個人的には、もっぱら刃体の鏡面仕上げ作業のために使用しています。
1000番で付いた研ぎ目を、短時間でスピーディーに消せるのが良いところ。これで仕上げれば、あとはコンパウンドで手磨きするだけで済み、鏡面仕上げが楽なのです。
購入前までは、キングS-1 を円盤形状に固めた砥石かと思っていましたが、さにあらず、6000番の焼結砥石でした。
焼結タイプですので、砥粒の隙間が効果的に働いて目詰りしにくく、レジノイドによく見られる『ごく僅かな沈み込み』もありません。
使いかたが判ってくると、作業効率がぐっと上がる良い砥石です。これと同じ材質の角砥石があれば入手したいと思いました(無いだろうけど)
ホームスカッター STD-180E 交換用砥石の入手先
● STD-180用 荒砥 #180 (amazon)
● STD-180用 荒砥 #180 (楽天で安い順に検索)
● STD-180用 中砥 #1000 (amazon)
● STD-180用 中砥 #1000 (楽天で安い順に検索)
● STD-180用 仕上砥 #6000 (amazon)
● STD-180用 仕上砥 #6000 (楽天で安い順に検索)
ホームスカッター STD-180E 買うならこちら
● 新興製作所 STD-180E (amazon)
● 新興製作所 STD-180E (楽天で検索)
外箱の画像

側面の画像(1)
箱の側面には、仕様(スペック)の記載があります。
(下に転記しておきます)
| メーカー名 | 新興製作所 |
| 品名 | ホームスカッター |
| 品番 | STD-180E |
| 電圧 | AC100V |
| 周波数 | 50/60Hz |
| 消費電力 | 125W |
| 消費電流 | 1.3A |
| 回転数 | 400/470min |
| 砥石寸法 | 180φx70φx20mm |
| 砥石粒度 | #1000 |
| 定格時間 | 20分 |
| 重量 | 5.0kg |

反対側の外箱側面。
こちらには、製品特徴の記載があります。
- 水量調整ダイヤルで、適量の注水が可能
- 水飛散防止クッションカバー付
- 角度、上下調節の出来る刃物ガイド
- 左回転、右回転のスイッチ付
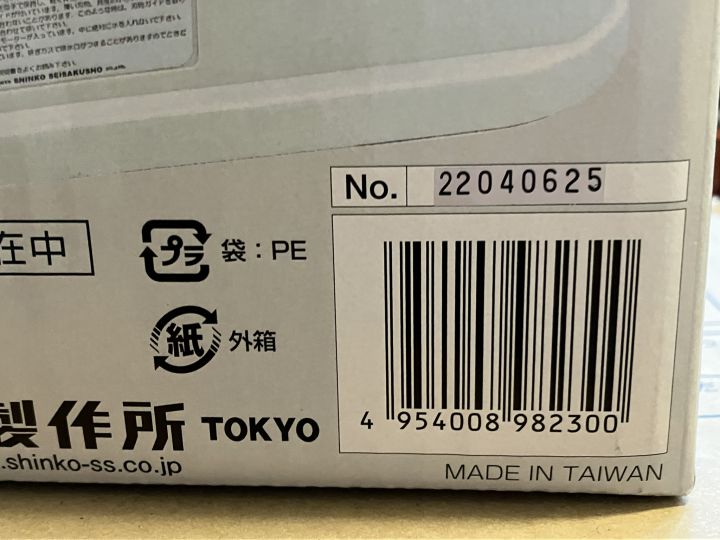
現行製品であるSTD-180Eの本体は、「台湾製」です。
以前は日本で製造していましたが、1999年発売のSTD-180D以降は、台湾での製造に変更されました。
「STD-180E」の前モデルは「STD-180D」、さらにその先代モデルは「ST-180C」となっており、マイナーチェンジを繰り返して熟成された、ロングセラーモデルです。
STD-180Eのモデルチェンジの具体的内容・歴史については、歴代のホームスカッターの項目をご覧ください(整理しました)

外箱上面の画像
ホームスカッター STD-180E - 目次
月寅次郎のおすすめ包丁
月寅次郎の包丁解説(裏話)
月寅次郎が実際に使っている包丁(使用包丁一覧)
月寅次郎の包丁カスタム(DIY作業手順)
包丁の研ぎ方、砥石、研磨など(砥石のレビュー)
月寅次郎プロフィール