
DIYで包丁を鏡面仕上げに(方法・手順)
包丁の鏡面仕上げ 目次

作業対象包丁:藤次郎 DPコバルト合金鋼割込 ペティナイフ(120mm)
-
包丁の傷を大まかに消す
-
包丁を研ぎ抜いて厚みを削ぐ(ブレード整形)
-
鏡面の下地出し(包丁の傷を消して下地を作る)
-
耐水ペーパーで傷目を細かくし、磨き作業に入れるかどうか確認
-
バフがけ(青棒、白棒、赤棒)で 包丁を鏡面に近づける
-
コンパウンドで包丁を鏡面に仕上げる
-
鏡面に仕上がった包丁
※ 合わせて読みたい、鏡面仕上げの事例
● 包丁のカスタム2 - 口金の鏡面仕上げ
● オピネルの鏡面仕上げ
● 和包丁のカスタム - 鏡面加工と漆塗り
※ 理解を深めたい、研磨の知識
● ピカールの粒度と研磨素材
● 「ピカールとブルーマジックを磨き比べた~!」は愚の骨頂
● ブルーマジックのウソ・ホント - 粒度、研磨剤、成分
● サンドペーパーはどれも同じではありません
包丁を鏡面仕上げにした 感想
今回は、軽く傷が入った状態から鏡面に仕上げる事になりました見た目は派手に傷が入っていましたが、それほど深い傷ではありませんでしたので、極端に時間もかかることなく、無事に仕上げることができました。DIYとしては上出来だと思います
また、三枚合わせのステンレス系包丁(ペティナイフ)ということで、側面鋼材の硬度も硬すぎることなく、切削研磨も快適に行うことができました
以前、炭素鋼のオピネルを鏡面に仕上げたときは、焼入れの入った全鋼ブレードの硬さと、腐食痕の深さに、根負けしそうになりましたが、それに比較すると、かなりスムーズに作業できたと思います
傷を消している途中で、「この際だから、ブレードを研ぎ抜いて刃抜けを良くしよう!」と方針変更してしまったため、最初に行った傷消しの研磨作業が無駄になってしまいましたが、結果的に抜けの良いブレードに仕上げることができ、満足しています
「切り抜けの良さ」は、包丁の切れ味の重要な要素の一つです
鋼材の種類も重要ですが、刃体形状を切削研磨して、どのような形状に仕上げるかも重要な要素で、刃物メーカーの腕の見せ所です
安価にもかかわらず、高級鋼材を売りにしている包丁は、このブレード成形にコストがかけられておらず、形状や仕上げが甘かったりします
DIYで包丁を鏡面にする際の、注意と心得
ここでは包丁の鏡面仕上げについて、具体的な作業内容を解説していますですがこれが、ベストのやり方とは申しません
元に戻ってのやり直しや、作業途中での方針変更など、紆余曲折もありますし、使用している道具は、自己保有の砥石や研磨材など、ありあわせのものです。(小さめのサンダーがあれば、砥石は使わなくても済むと思いますし、最終段階での『手磨き』も省けると思いますが、持っていないのでこのような工程をたどりました)
ネットに書いてあることを鵜呑みにしない
ネットに書いてあることを鵜呑みにして、そのまま作業しても、たいていうまくいきませんこのページを見て、鏡面仕上げの参考にされる方は、「あくまでも参考」だと考えて、自分の作業環境、所有工具、対象となる包丁に合わせ、最適な方法を模索してみてください(こうやれば鏡面になるというものではありません)
目で見て、考えて判断する、安易に番手を上げない
重要なのは、研磨材の食い付き具合や削れ具合などを、そのつど自分の目でよく確認し、判断を適宜修正しながら、作業を進めていくことです。次の番手に上げてよいのか、それとも下地の段階に戻って傷を取り直すのか、判断するのは自分自身です。
大抵の人は、 『一定時間磨いたから』というイージーな理由で、根拠もなしに次の番手に上がりがちです。
傷が取り切れていないので、あえて番手を下げ、前段階からもう一度やり直すというのは、勇気のいる決断ですが、これができる人は大抵うまくいきますし、上達も早いものです。
光源を上手に使う
「目で見て考えて・・」と書きましたが、漫然と見るだけでは正確な情報は得られませんデスクライト等を活用して光源にかざし、様々な方向から光を当てて、研ぎ目の深さや下地の状態を把握しましょう
特定の方向から光を当てることで、研ぎ傷が見えたり見えなかったりします
ヘアライン状の一定方向の研ぎ傷を付けた場合は、特にそうなります
光を上手に使うことができなければ、今、何がどうなっているのか、的確に把握することができません。
状況把握なしに判断はできませんし、そのような状態ではクオリティの高い鏡面は得られにくいものです。
作業対象と、作業環境に合わせた作業を
人によって作業対象は作業環境はさまざまですそれぞれの包丁によって、傷の深さや鋼材硬度が異なります。
三枚合わせの包丁の場合、側面材の硬度はどの製品もたいして変わりませんが、一枚物の包丁の場合(海外製の包丁に多い)使用されている鋼材によっては、かなり硬度が異なります
この場合、価格が高価な製品ほど硬度の高い鋼材を使用していることが多く、条件によっては、なかなか削れなかったりします。また、逆に柔らかめの鋼材の場合は、研磨粒子が深く食い込んでしまって、かえって傷になりやすいこともあります
丁寧に根気よく、そして己を制御する
鏡面仕上げにおいて重要なのは、『丁寧さと根気と、セルフコントロール』です決して簡単に終わるものではありませんので、必ず休憩を入れながら、できれば複数日に分けて作業しましょう
そうすることで作業が丁寧になり、結果としてきれいな鏡面に仕上ります
そういった部分が「セルフコントロール」です
自分自身を上手に操り、集中力が落ちる前に休憩を入れ、思い通りにならずにイライラしてきたら作業を中断します
時間に余裕があって、精度の高い作業ができるときだけに、自分に作業をやらせるのです
なお、包丁が一本しかない場合は日数をかけて作業することが難しくなります。100均の包丁でも構いませんので、代替的に使用できる包丁を用意することをおすすめします
※ 追記
包丁のカスタム2 - 口金の鏡面仕上げ のページにて、サンドペーパーの番手ごとに、6枚の仕上がり画像を掲載しました
光源を上手に使うことや、磨く方向を変えること、同じ番手でも3段階に分ける考え方など、かなりマニアックな磨きテクニックを公開しています(鏡面仕上げにこだわりたい方は、参考にしてください)

このような、表面ゴリゴリの状態からスタートして…

サンドペーパーを使って、ここまで仕上げました(実際にはこの状態からさらに施工しました)
画像をクリックしても、該当ページにジャンプ可能です
● 関連ページ:藤次郎 DPコバルト合金鋼割込 ペティナイフを使ってみた
● 関連ページ:藤次郎のDPコバルト合金鋼は、本当にV金10号なのか?
刃物記事一覧 に戻る
月寅次郎の本(著作)
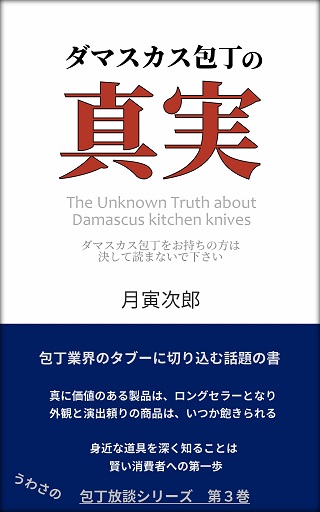 ダマスカス 包丁の真実 420円 |
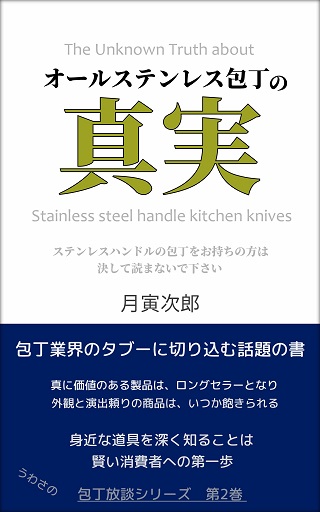 オールステンレス 包丁の真実 340円 | |
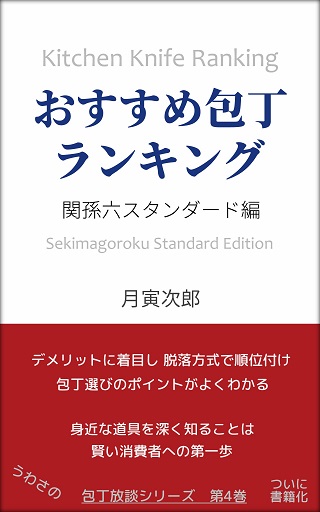 おすすめ包丁ランキング 関孫六スタンダード編 530円 |
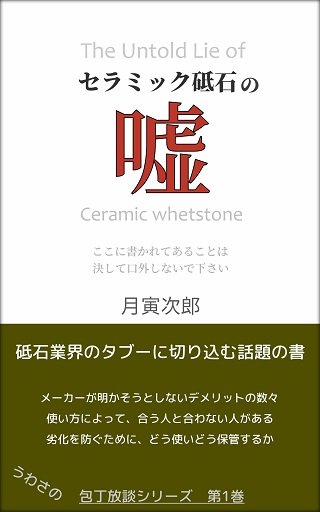 セラミック 砥石の嘘 340円 | |
|
一部の本の紹介です。全作品は、著作一覧ページ をご覧ください。 書籍価格は2024年4月時点。Kindle Unlimited の無料期間を使えば、全巻読み放題 | ||
当サイトの内容が本になりました!
このページを読んで役に立ったと思ったら、投げ銭代わりに上の本でも買ってやって下さい。
サイト内にamazon広告が貼ってありますが、広告経由で買い物して頂けると助かります。
当サイトには、レンタルサーバー費やドメイン管理料などのコストがかかっており、書籍の売上金はそれらの費用に充当されます。(ワタシの執筆料は0円でタダ働きです)
追記:稚拙な解説ページを鵜呑みにしないよう、気をつけましょう
補足として記載しておきますネット上に掲がっている鏡面仕上げの解説ページは、玉石混交です
先日、「包丁を自分で鏡面仕上げできるのか?」というページに目を通してみました
内容を一言でいうと、「2時間あれば、あなたも自分で包丁を鏡面に仕上げられます」というものでした
しかし、よく読んでみると、実際に鏡面に加工しているのは、和包丁(鎌型薄刃包丁)の平の部分であり、洋包丁の鏡面仕上げに時間がかかる事については、全く言及がありません
ちなみにその記事を書いているのは、なんと堺の老舗の包丁メーカーなのです。
これにはさすがに「いかがなものか?」と思いました
包丁を製造・販売している業者が、消費者の誤解を招くことを、平気で書いて良いのか?という感じです
正直言って、良識を疑います
「包丁の鏡面仕上げは、2時間でできる」というミスリード
前述のページで、鏡面に加工しているのは、和包丁の平(ひら)の部分ですこの「平」を鏡面に仕上げるのは、和包丁の世界ではよくあるパターンで、商品価値を上げるために、最初から平を鏡面に加工した和包丁も多数販売されています
平(ひら)の鏡面仕上げは、それほど難しくない(むしろ簡単な部類)
実際のところ、平(ひら)というのは、その名の通りに平面ですので、ベルトサンダーで番手を上げていき、最後にバフがけすれば、難なく鏡面に仕上がりますベルトサンダーなどの電動工具が無く、手作業で磨き加工を行う場合でも、平面であるがゆえに当てゴムなどを使って均一な加工を施しやすく、包丁やナイフの中では「最も簡単な鏡面仕上げ」の一つと言えるでしょう
形状だけでなく、硬度的にも鏡面に仕上げやすい柔らかさ
平の鏡面が簡単な理由は、形状だけではありません鋼材的にも、鏡面に加工しやすいということができます
通常の和包丁の「平(ひら)」の部分は、軟鉄が使用されています(本焼きを除く)
この「軟鉄」という素材は、鋼(はがね)やステンレス刃物鋼とは全く異なり、炭素含有量が0.08%以下と非常に低く、包丁の刃体に使用される金属素材の中では、ダントツに柔らかい素材です(そもそも刃物鋼ではないので硬度が低く、磨きやすいのです)
わたしも実際にやったことがありますが、具体的な工程・手順については、下のページをご覧ください
● 和包丁の平(ひら)を鏡面に仕上げた例
新品の包丁なら、傷や錆を取って下地を出す必要もない
さらに新品の包丁を鏡面に加工する場合は、難易度が大幅に下がります長年使用された包丁を鏡面に仕上げるのとは異なり、傷や錆を除去して下地を出す必要がないからです。ほぼ下地の出ている状態からスタートすることになり、作業時間が大幅に短縮されます
厳密に言うと、和包丁の平は、通常「木砥」で仕上げられていることが多く、一種のヘアライン仕上げです。職人によって表面処理された木砥目は、均一に仕上げられた凸凹のようなものですので、既に下地が出ていると言っても過言ではありません
さて、改めてポイントを整理してみましよう
包丁の鏡面仕上げの難易度を左右する三要素
鏡面仕上げの難易度(必要な作業時間)は、以下の3点によって大きく左右されます-
刃物の形状(平面か曲面か、峰やアゴ回りの加工も行うか)
-
素材の硬度(側面も刃物鋼材の一枚物の包丁>ステンレス系の3枚合わせ包丁>軟鉄)
-
下地の状態(深い傷や、ピンホール状の錆の有無)
上記は、鏡面仕上げの作業時間を大きく左右する、非常に重要な要素です
これらに全く言及せず、最も簡単な和包丁の平を鏡面にして、「2時間で鏡面にできるよ!」と言ってのけるのは、これはもう、消費者のミスリードを誘っているとしか思えません
そのページには、一応「包丁の種類にもよりますが」という一文もあるのですが、それでは不十分です
なにしろ、そのページを書いているのは、大阪は堺市に所在を持つ包丁ブランドなのです。和包丁だけではなく、洋包丁も販売しているのです。(海外販売にも積極的です)
わたしがここで言及したことを、知らないわけがありません
万一知らないようであれば、包丁の仕上げについて知識不足であり、ど素人と言って構わないでしょう(包丁を販売するに値しません)
また、知っていて敢えて書かないのであれば、それは悪質です(わざと消費者のミスリードを狙っているのですから)
消費者を思いやるのではなく、最初から騙すつもりならば話は別ですが、包丁メーカーとしての矜持があるのであれば、「包丁の種類にもよりますが」の一文で煙に巻くべきではありません
はっきりとした説明が必要でしょう
包丁の鏡面仕上げの作業時間は、実際どのくらいなのか?
それでは、はっきり説明するとどうなるのか、実際にここで解説してみましょう前述の『和包丁の「平」を、2時間で鏡面に仕上げる場合』をモデルとして、同じ環境(道具)で作業した場合、洋包丁では何時間かかるのでしょうか?
一般的なステンレス洋包丁の場合は10~12時間程度は、見ておいた方が良いと思います
新品商品で、刃渡りは同程度、側面材の付いた「3枚合わせ」を仕上げる場合です
「平」が、包丁に占める表面積は、たったの1/4程度でしかありません
残りの面積3/4のうち、1/4が切刃となり、2/4が裏すき(裏面)となります
洋包丁には「平」という概念がなく、刃体全体が作業対象となりますので、面積は4倍となり、作業時間を単純に4倍すると、8時間かかることになります
また、磨く素材が軟鉄より硬いですので、研磨に時間がかかります
SUS410などのステンレス系刃物用側面材の場合、軟鉄と比較して、1.5~2割増し程度の作業時間が必要になるでしょう。計算上では12時間~16時間となります
「3枚合わせ」や「割り込み」ではなく、側面材の無い一枚物の包丁の場合、側面も刃物鋼としての硬度を持っています。このため、さらに時間がかかります
安物の包丁であれば、硬度がHRC56~57程度なのでまだ良いですが、耐摩耗性に優れたVG10などの一枚物のステンレス包丁の場合は、なかなか研磨が進みません
そのため、15時間~20時間かかってもおかしくありません(ここまでくると実際にやるのも大変ですので、わたしの場合電動工具を併用することも多いです)
こうやって見ると、「サンドペーパーと白棒、青棒を使って、2時間で包丁を鏡面にできるよ!」というのは、和包丁の平だからこそ可能なことであり、和包丁の所有者自体が少ないことも考慮すれば、あまり一般的なケースとは言えません
わたしも個人的に刃物としての和包丁が好きで、実際に5本ほど所有しています
刃を研ぐ際に、時々平を磨いたりしています。しのぎ筋がきっちり出た和包丁は、見ているだけで背筋が真っ直ぐになる思いです

薄刃包丁で桂剥きをしていると、その切れ味に惚れ惚れします
そもそも刃の角度が違う(鋭角)というのもありますが、洋包丁では味わえない、片刃の素晴らしさというものがあるからです
和包丁は、世界に誇る日本の文化の一つであり、何世代にも渡って継承されてきた技術的な遺産です
だからこそ、和包丁を取り扱うメーカー各社には、いい加減なことを書いて欲しくないという思いがあります(自分が販売している和包丁の価値を、自ら貶める行為だからです)
上の画像は、わたしが実際に使っている和包丁です
柄のついていない方の一本は、柄付する前に撮影したものです。柄付や鏡面、漆塗りなど、カスタムのやり方、手順は、下のリンク先を見るとわかると思います
● 和包丁のカスタム(薄刃包丁)
● 堺刀司 薄刃包丁(岩国作・カスタム)
● 有次の包丁(アジ切)
● 水野鍛錬所・源昭忠の薄刃包丁
(こちらは特にカスタムしていませんが、かなり使い込んでいます。桂剥きの画像はこちらで見られます)
月寅次郎が使っている和包丁の一覧
誤解を招く記事を垂れ流す業者ほど、ダマスカス包丁をすすめてくる
こういったミスリードを誘う業者は、よく「ダマスカス包丁は、とてもおすすめ!」と言って勧めてきたりするんだよね・・・と、思いながら、くだんのサイトを眺めていたら、本当にダマスカス包丁を勧めていました
「家庭用で迷ったらこれ」、「お勧め・人気No1」、「ミルフィーユ模様がカッコいい」と推している有様です
もう、呆れて物が言えません
ダマスカス包丁がおすすめできない理由は、こちらのページで詳しく解説していますので、興味のある方はご一読下さい
● 刃物記事一覧 に戻る